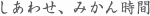果物がもっと好きになる「猛暑に食べたい夏野菜」
野菜ソムリエ 知久幸子さん vol.499
=====================================
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
今年もすでに猛暑日が続き、夏バテ気味の方も多いのではないでしょうか?
そんな時にこそ食べてほしいのが、今が旬の夏野菜です。
夏野菜は水分とカリウムを多く含んでいるという特徴があります。
どちらも汗と一緒に流れ出てしまうので、
夏場は特に不足しがちになります。
カリウムが不足すると筋肉に疲労が蓄積しやすくなり、
食欲も減退して夏バテ状態になるので、
日々の食事で夏野菜をこまめに摂ることで水分とカリウム不足が補えます。
夏野菜の代表格的なトマトの酸味であるクエン酸は、
胃の働きを活発にしてくれます。
茗荷に含まれる香り成分でもあるαピネンにも、
食欲を促進する作用があるそうです。
きゅうりは95%もの水分を含み利尿作用もあるので、
体の内側の熱を外に運び、体を冷やすと言われています。
これらを刻んで塩昆布で和えるだけでも美味しいですし、
夏野菜を賢くとり入れて猛暑を乗り切りましょう。
|
みかんでもっと笑顔になる「七味の日」
野菜ソムリエ 玉之内祐子さん vol.557
===============================
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
本日、7月3日は数字の語呂合わせから「七味の日」。
海外の旅行者の方にもお土産として人気の高い日本が誇る香辛料です。
お気に入りのメーカーのものを常備しているという方も多いのではないでしょうか?
七味唐辛子はその名の通り、
(基本的には)七種類の薬味や香辛料を調合して作られるミックススパイスです。
中身は主に『唐辛子・胡麻・陳皮(ちんぴ)・けし・麻の実・山椒・紫蘇の実または青海苔』であることが多いですが、
各メーカーによって独自の配合でオリジナルのものを作り出していて、上記に限りません。
関西では淡口しょうゆに合わせた香りが立つ配合になっていたり、
関東では濃口しょうゆに合わせたしっかり辛味が効く配合になっていたりするので、
使い分けるのも乙です。
また、最近はゆず七味やかぼす七味、
ガラムマサラ七味など変わり種も多数あり、
構成を見るだけでも楽しいのでぜひ注目してみてくださいね。
|
みかんでもっと笑顔になる「熊本の赤ナス」
野菜ソムリエ 玉之内祐子さん vol.555
===============================
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
蒸し蒸しと暑くなってきました。
今回は夏野菜の代表格「ナス」の中でも熊本県の特産品「赤ナス」をご紹介します。
熊本の赤ナスは大正時代から生産されている伝統野菜で、
古くから食べられていました。
しかし、どうしても各農家で品質にばらつきがあったため、
熊本県農業研究センターが品種改良して
2002年に「ヒゴムラサキ」という新品種を開発。
以後ブランド化を進めています。
このヒゴムラサキは一般的なナスと比べて非常に長く太いのが特徴で、
果皮も濃い紫ではなく、赤紫色です。触れるとわかるのですが、
見た目に反して軽く、ふわっとやわらかさを感じます。
生で食べられるほどアクが少なく、
加熱すると甘みが際立ちトロっとした食感が楽しめます。
ナスは夏野菜の一つではありますが、
このヒゴムラサキは真夏をはずした2月から6月と9月から11月が出回り期。
ぜひ見つけて試してみてくださいね。
|
果物がもっと好きになる「新生姜」
野菜ソムリエ 知久幸子さん vol.496
=====================================
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
先日の6月15日は「生姜の日」で、記念日ということで、
アンテナショップや青果店でイベントが開催されていました。
生姜とひとことで言っても大きく分けて2つに分かれます。
主にハウスで栽培され、3月から8月にかけて収穫され、
収穫後すぐに出荷される新生姜と、
露地栽培で10月に収穫され、
貯蔵庫で保存しながら周年出荷される囲い生姜です。
普段、生姜は薬味として少しずつ使われることが多いですが、
今の時期に出回っている新生姜は、色も白く水分をたっぷり含んでおり、
辛みも穏やかなので、実は他の野菜を同じように料理にたっぷり使うことが出来ます。
新生姜の活用法としては「甘酢漬け」がポピュラーですが、
生姜日本一の産地高知県の春野では、
千切りを鰹のタタキにたっぷり乗せる他、
きゅうりと混ぜてサラダにして食べるそうですよ。
次回は新生姜を使ったレシピをご紹介したいと思います。
お楽しみに!
|
みかんでもっと笑顔になる「やまがた紅王」
野菜ソムリエ 玉之内祐子さん vol.554
===============================
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
6月といえば「さくらんぼ」の季節。
いよいよ旬の到来です。
定番の「佐藤錦」や近年人気の「紅秀峰」など、品種は様々ありますが、
大注目の新品種「やまがた紅王(べにおう)」をご存じでしょうか?
やまがた紅王は2023年に本格販売が開始されたばかりで、
なんと2Lサイズ(500円玉大)以下は認められないという、
非常に大粒で美しいさくらんぼです。
レーニアと紅さやかを掛け合わせたC-47-70という品種に
紅秀峰を掛け合わせて誕生。
国内最大のさくらんぼ生産を誇る山形県が開発した期待の新星です。
収穫期は6月下旬から7月上旬。
酸味が少なくバランスのとれた味わいで果肉の大きさからくるジューシーさは抜群。
というのもさくらんぼの種はどれもほぼ同じサイズ。
粒が大きければ大きいほど果肉をたっぷり味わえるのです。
ツヤがあり、きれいに色付く上に、
果肉がかためで日持ちもするので贈答用にもぴったり!
ぜひ試してみてくださいね。
|
果物がもっと好きになる「白子町の玉ねぎ」
野菜ソムリエ 知久幸子さん vol.494
=====================================
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
5月に入ると関東地域で収穫シーズンを迎える玉ねぎ。
玉ねぎの産地として有名な千葉県の白子町に行ってきました。
白子町は千葉県の太平洋沿いに位置し、
すぐ近くに海水浴場としても有名な九十九里浜があります。
玉ねぎ畑もサラサラの砂地で水はけが良く、
畑を訪問した日の前日は終日雨模様でしたが、
太陽が顔を出した当日の昼頃にはサラサラに乾いていました。
同じ千葉県内でも落花生農家の友人は、
雨の翌日は土がぬかるんで仕事にならないと驚いていました。
土と砂とで、こんなに差が出るとは!
このミネラルを含んだ水はけの良い砂地と、
海から届く潮風が、辛味の少ない生で食べても甘さを感じる玉ねぎを育てるそうです。
収穫体験を受け入れている観光農園もあり、
今年は特に大玉サイズが豊作だそうで、
ゴールデンウィーク中は家族連れの車で渋滞が出来たそうです。
「白子の玉ねぎ」見かけたらぜひご賞味ください。
|
みかんでもっと笑顔になる「ヨーグルトの日」
野菜ソムリエ 玉之内祐子さん vol.550
===============================
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
5月15日は「ヨーグルトの日」。
ヨーグルトの乳酸菌が身体にいいことを発見し、
ノーベル賞を受賞したロシアの生物学者イリア・メチニコフ博士の誕生日に由来します。
今回はそんなヨーグルトの日にちなんで、
ヨーグルトと一緒に食べるのにおすすめの野菜や果物を紹介します。
まずは、オリゴ糖を含むバナナや、キウイフルーツやイチゴ、リンゴやカンキツ類など、
水溶性食物繊維を豊富に含む果物はヨーグルトとの相性ぴったり。
腸内細菌が喜ぶ食べ合わせで腸活にもおすすめです。
また、ヨーグルト×野菜×スパイス×塩の組み合わせは
インドなどでは定番のサラダ(=ライタ)として人気です。
ライタとはヨーグルトのサラダで、カレーの付け合わせとしても欠かせません。
刻んだキュウリやアボカド、赤玉ネギやサッとゆでたオクラなどをヨーグルトと和え、
クミンなどのスパイスやハーブ、塩で味付け。
簡単なのでぜひ試してみてくださいね。
|
果物がもっと好きになる「茨城の春メロン」
野菜ソムリエ 知久幸子さん vol.492
=====================================
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
春メロンが出回る季節がやって来ました!
日本一の生産量を誇るのは茨城県なのですが、
北海道や静岡県産のメロンに比べると認知度が低いようなので、
茨城県民の知久が茨城メロンの魅力をご紹介したいと思います!
1つめのポイントは「手頃さ」です。
安いものだと一玉1,000円前後で購入できますし、
贈答用でも一玉5,000円もしません。
その理由は栽培方法にあります。
無加温のビニールハウスに、地這えで栽培し、
1つの苗から数個収穫します。
そのため加温による燃料費の上乗せがなく、
一玉当たりの単価が安くなります。
2つめのポイントは栽培に適した土地であること。
メロンは湿気を嫌います。
出荷量1位の鉾田市は、関東ローム層という水はけの良い土壌で太平洋に面しており、
心地よい潮風がハウスを通り抜け湿度を逃してくれます。
栽培品種も豊富で、
イバラキングというブランド品種もあるのでぜひ一度ご賞味くださいね!
|
みかんでもっと笑顔になる「しどけ」
野菜ソムリエ 玉之内祐子さん vol.549
===============================
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
春を通り越して夏のような暑さの日もありますが、
暦の上ではまだまだ春。夏はまだ待ってほしいところです。
さて、春といえば山菜の季節。
ほろ苦さや独特の香りを楽しめる山菜は、日本各地に自生する山の宝です。
タラの芽やうど、うるいやこごみなど様々ありますが、
「しどけ」という山菜をご存じでしょうか?
葉がモミジに似ているため、正式名称は「モミジガサ」といいます。
そのモミジのような葉が開く前は、傘のように折りたたまれていて、
その葉が開き始めるころが収穫のタイミング。
山の中の沢の近くの斜面などに自生していることが多いそうです。
ほろ苦く大人の味で、シャキッとした歯ごたえも魅力。
ファンが多く、一度はまると病みつきになるおいしさです。
葉ももちろん食べられるのですが、
主に茎を食べる山菜で、サッと茹でてお浸しに、
またはくるみ和えやごま和えがおすすめです。
「しどけ」ぜひ食べてみてくださいね。
|
みかんでもっと笑顔になる「八十八夜」
野菜ソムリエ 玉之内祐子さん vol.548
===============================
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
2024年5月1日は、立春から数えて88日目で八十八夜。
古くからこの日は、気候が安定して『農業に本腰を入れる日』の目安とされてきました。
そして、茶摘みの歌でも知られるように
八十八夜といえば『新茶』のイメージが強いですよね。
お茶の葉は1年に3〜5回の収穫が可能で、
中でも最初に収穫される新茶が甘み・旨みがギュッと詰まっていて香り高く、
最もおいしいとされています。
そのためこの八十八夜を目安に
お茶農家さんたちは1番おいしい新茶を見極めて収穫をするそうです。
やはり名産地といえば静岡県ですが、
他にも三重県や京都府などが有名です。
そして実は九州各県にも日本屈指の名産地が点在しています。
鹿児島県の知覧茶や福岡県の八女茶、長崎県のそのぎ茶など
、おすすめのお茶が満載です。
八十八夜に摘まれたお茶を飲むとその一年は無病息災で過ごせるとされているので、
ぜひお好きな産地や茶園の新茶を楽しんでくださいね。
|